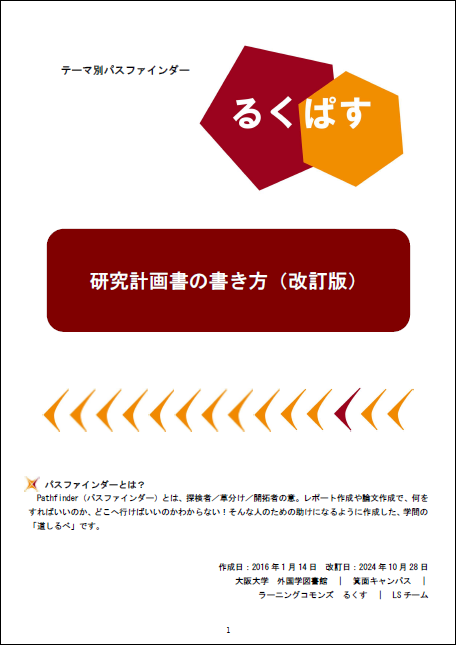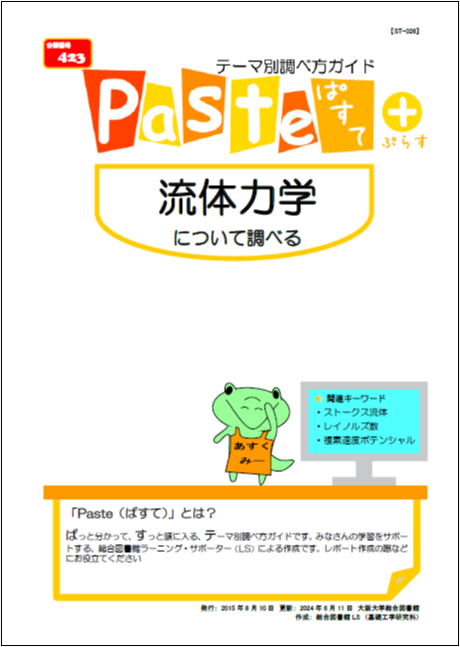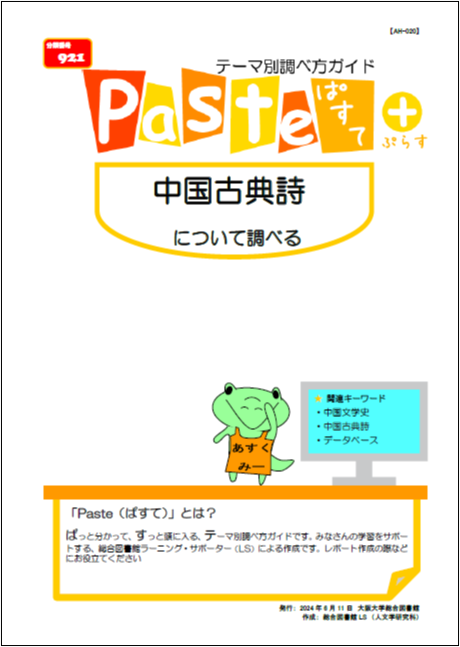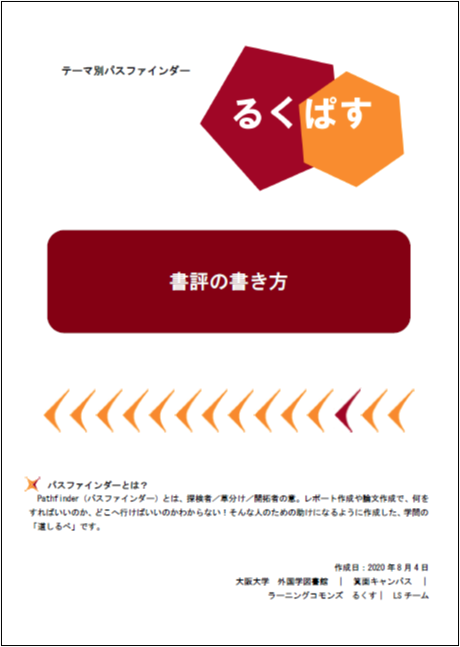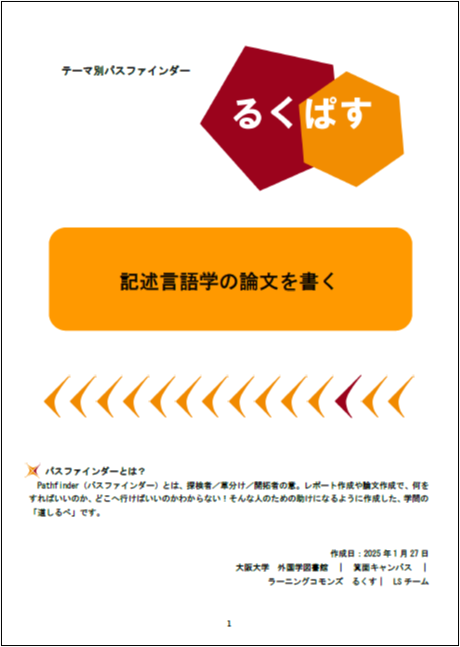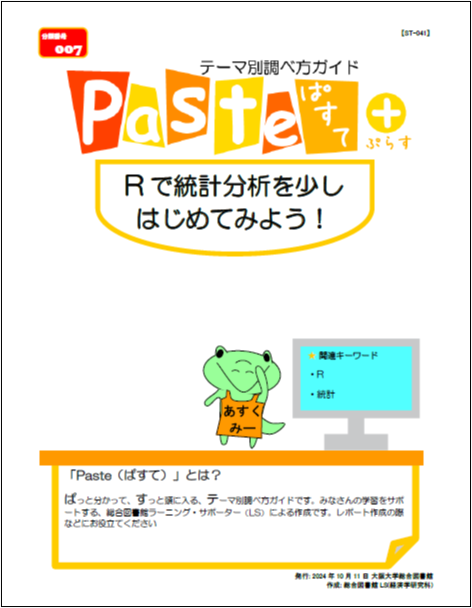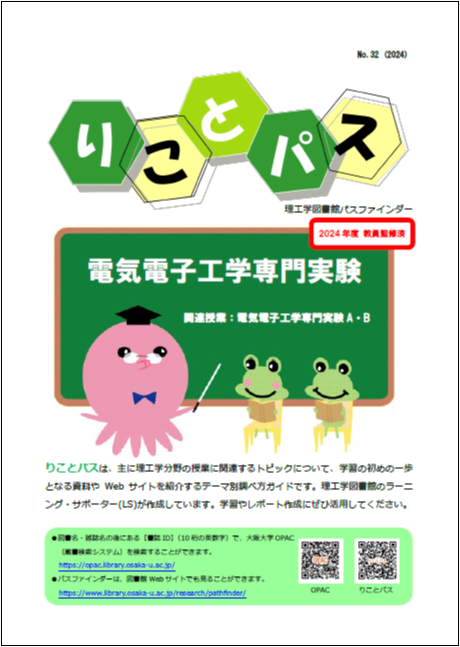【LS FORUM】(大学院生スタッフから)「パスファインダー」
大阪大学附属図書館では、3館(総合図書館・理工学図書館・外国学図書館)で学生のみなさんの学習をサポートする大学院生スタッフ「ラーニング・サポーター(LS)」が活動しています。
今回のLS FORUMでは、LSの活動のひとつであるパスファインダーについて特集します!
パスファインダーとは、あるテーマや話題について、学習の初めの一歩となる資料やWebサイトを紹介したリーフレットです。
附属図書館のWebサイト(パスファインダー)では、歴代のLSが作成したパスファインダーを200件以上公開しています。LSが専門を活かして、調査に役立つ資料や、検索のためのキーワード、有用なサイト、ツールをまとめていますのでぜひご活用ください。
企画1 LSに聞きました!「あなたのおすすめのパスファインダーは?」
2024年度のLSにおすすめのパスファインダーを教えてもらいました!
研究計画書の書き方(改訂版)
LSからのコメント
学部生の方にとって、院試の一番のハードルは研究計画書なのではないでしょうか?このパスファインダーでは、過去に院試を突破した我々LSが進学の準備の際に参照した本を多数挙げています。また、研究計画書だけではなく、「大学院での研究生活をイメージするために」というコーナーもあり、大学院に進学したい・検討している人に役立つ情報が詰まっています!(人文学研究科 M2)
流体力学
LSからのコメント
流体力学について学びたい大学生必見!このパスファインダーでは、流体力学について学ぶ初心者のために、最初に読むべき教科書や、有用なナビゲートツールが紹介されており、流体力学に対する理解を深めるのに役立ちます!また、レポート作成に困った際にも役立つので、学びの質を高めるためにもぜひ活用してみてください!(工学研究科 M1)
中国古典詩
LSからのコメント
中国の古詩に興味を持っている初心者に、「最初の入門書」として日本語で著された読みやすい書籍を多数紹介しています。日本では古来より中国の古詩を勉強する伝統があり、近代以降の日本には中国文学を研究する大学者が多くいます。彼らが書いた概説書にも長年の研究成果が含まれるので、古詩の鑑賞に不可欠なおすすめの本です。(人文学研究科 M2)
書評の書き方
LSからのコメント
授業の課題やゼミで書評レポートが課されたとき、何をどう批評し評価するのか、方法を知っていますか?これを読めば書評の骨組みが分かります。「何を書けばよいのか、どう書けばよいのか、まったくわからない…」という人も、基本に立ち返りたい人も、一度チェックしてみてください。(人間科学研究科 D2)
企画2 パスファインダーを作成したLSにインタビュー!
各館のLSを代表して3名のLSから、作成したパスファインダーについて熱く語ってもらいました。
1 記述言語学の論文を書く
人文学研究科 D1
パスファインダーを作成するにあたり、どのようにテーマを決めたのか
「私の専門は言語学です。アフリカでフィールドワークをしています。」と自己紹介をすると、アフリカの奥地まで足を運んで、名前も知らない言語の調査をしていると思われることがあります。実際には、私はハウサ語という西アフリカではとても有名な言語(話者は1億を超すとも言われる)の変種をガーナの都市で記述しています。
我々が生きる21世紀のグローバル世界では移動が当たり前の時代です。周りをじっくりと見渡すと、多様な言語空間が広がっていることに気が付きます。留学生と出会ったり、外国にルーツを持つコミュニティに足を運んだりすることで新たな言語に出会うことがあるかもしれません。また都市や大学に特有のスラングや若者ことばなど自分で「新言語」を発見することもあるでしょう。
このようにアマゾンやアフリカの奥地に行かなくても言語の調査はできますし、むしろ身近な場所にこそ研究のヒントが隠れています。多くの学部生が様々な言語と出会い、それを学問に繋げてほしいという思いから「記述言語学の論文を書く」というテーマを設定しました。
作成時に楽しかったことや印象に残っていること、やりがいを感じる瞬間
大学院生は、初対面の人に自分の研究分野や研究対象について簡潔に分かりやすく説明することが求められます。またその分野を一から学ぶためのおすすめの文献を即座に提示することも時として求められます。
今回、新しくパスファインダーを作成するにあたり、当該分野の初学者向けの本を包括的かつ網羅的にリストアップしました。次に学部生が比較的読みやすい本を厳選するために、様々な本をもう一度最初からじっくりと読むことにしました。そうすることで、当該分野の研究の歴史を体系的に整理することができました。また私が研究の道に進むきっかけとなった思い出の本を再読することで、少し勉強のモチベーションとなったのを覚えています。
今なら、これから言語の記述をしたいという人や具体的な言語の記述の方法で悩む人に向けて是非読んでほしい本をいくつか列挙できますし、自分の研究テーマについてその魅力を熱く語ることもできます。
2 Rで統計分析を少しはじめてみよう!
経済学研究科 D3
パスファインダーを作成するにあたり、どのようにテーマを決めたのか
Rという統計分析用プログラミング言語に関するパスファインダーを作成しました。テーマを選定した理由は主に二つあります。一つ目は、すでに対面形式でRの初心者向け講習会を行っており、その内容をパスファインダーとして形にすることを職員から提案されたためです。二つ目は、Rに関する良質な文献案内が見つかりにくい現状があったためです。
Pythonのような汎用的なプログラミング言語と異なり、Rは統計分析に特化しているため、学ぶ層が限られる傾向があります。その結果、ネット検索で「R 初心者 参考書」と調べても、古い情報や入門的でない内容、信頼性に欠けるサイトが目立つという問題があります。このような状況から、Rのパスファインダーが必要だと判断しました。また、大阪大学ではラーニング・サポーターが既存のパスファインダーを定期的に更新しています。このため、足がかりとして一つ作成しておくことが、将来的により良い案内資料の基盤になると考え、Rのパスファインダーを作成することにしました。
作成時に楽しかったことや印象に残っていること、やりがいを感じる瞬間
Rに限らず、入門書や参考書を読むことが好きであるため、それらをまとめる作業は非常に楽しいものでした。作成の過程では、複数の参考書を比較し、どの情報が有用で、有用でないのかを検討する良いトレーニングとなりました。また、推薦する立場として、本の内容を十分に読み込んだ上で推薦ポイントを記載する責任感を持つことが求められました。
今回作成したパスファインダーは、通常の参考文献一覧とは異なり、簡単なRの操作演習も付け加えました。これにより、対象となる学生が何を目的にこれを読むのか、各作業をどれだけ細分化する必要があるのか、すべてを読み通すのに必要な時間はどれくらいか、どの順番で学習を進めればスムーズであるのかといった点を意識することができました。このような視点は、ラーニング・サポーター業務における質問対応や相談対応にも役立つものであると感じています。
さらに、現時点で満足のいく形で、入門書への案内を目的としたパスファインダーを作成できたことは大きなやりがいでした。この作業を通じて得た経験は、今後の業務や他の資料作成にも有益であると確信しています。
3 電気電子工学専門実験
工学研究科 M1
パスファインダーを作成するにあたり、どのようにテーマを決めたのか
パスファインダーを制作するにあたり、私自身が受講した経験があることに加え、苦労した記憶のあるテーマを選びました。電気電子工学専門実験は学部3年における必修科目であり、他の授業とは違い実験をメインに授業が進行していくため理解が追い付かないまま先に進んでしまうことが多々ありました。また、実験結果や考察をまとめるレポートについても作成した経験がほとんどなかったため、非常に苦労した覚えがありました。そこで私は、電気電子工学専門実験を履修する学生たちが実験内容の理解やレポートの作成で困ることの無いよう、パスファインダーを作成することに決めました。
作成時に楽しかったことや印象に残っていること、やりがいを感じる瞬間
パスファインダーの作成を通じて印象に残ったのは、授業内容が年度により変化しているということです。電気電子工学専門実験では、電気系と電子系、それぞれ複数の実験テーマについて学ぶのですが、そのテーマ数が10年間で約2/3にまで減少しているという事を知りました。そのため授業を担当している教員の方々や、最近実際に授業を受けた後輩などに授業内容を確認し、最新の授業内容を反映できるよう心がけました。このような経験から、パスファインダーは一度執筆したら終わりではなく、定期的にその内容をチェックし、加筆修正を加えることが重要であると実感しました。
また、パスファインダーを作成する上でやりがいを感じたのは、パスファインダーを手に取ってくださる学生がいらっしゃった瞬間です。私は普段パスファインダーの棚がよく見えるLSデスクにて従事しているため、その前をたくさんの方々が通りかかる様子が目に入ります。多くの方がその前を通り過ぎていく中、パスファインダーの前で立ち止まったり、そのうち1部を手に取ってくださったりする方がいらっしゃいました。そんな時、パスファインダーが学生の皆さんの役に立っているという事を実感でき、やりがいを感じることができました。私の作成したパスファインダーが、いつか後輩の皆さんのお役に立てば光栄です。